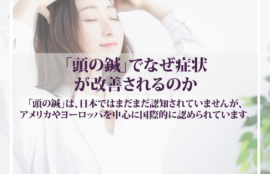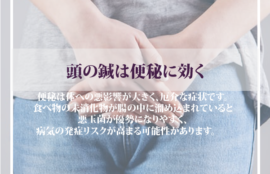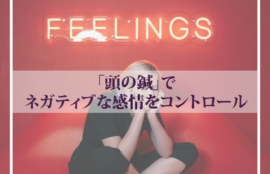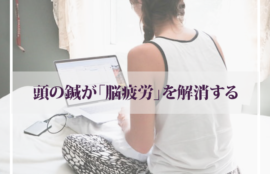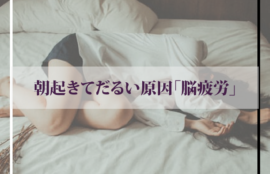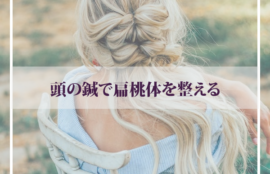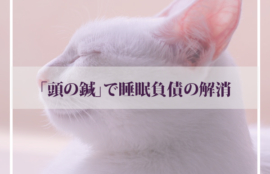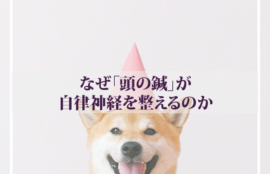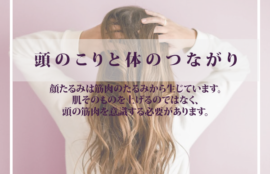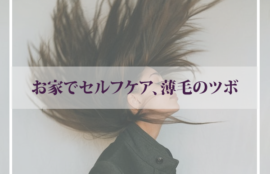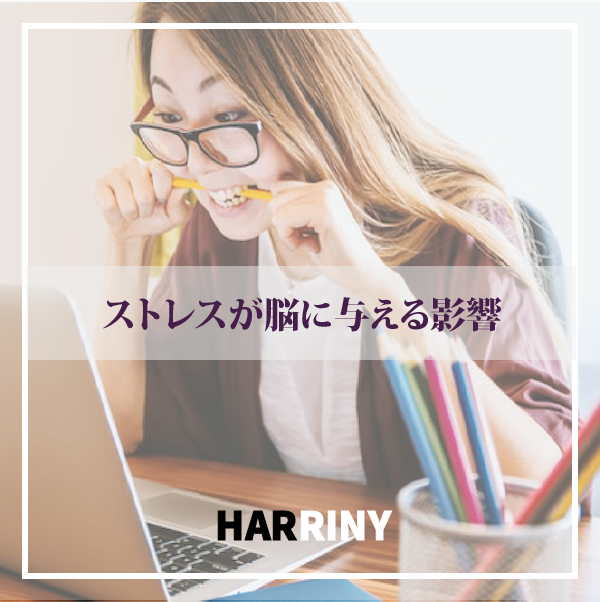
職場、家庭、人間関係、経済的な不安、仕事に関することなど、日常生活の中で、私たちがストレスを感じることがよくあります。さらに新型コロナウイルスに対する不安から、より多くのストレスを感じている人もいます。
ストレスと聞くと、嫌なことや辛いことを連想される方が多いかもしれません。しかし、実はうれしいことも楽しいこともストレスの原因になります。毎日を快適に過ごすために、まずはストレスを正しく理解しましょう。
ストレスとは
一般的には、ストレスは嫌なことに対して我慢するなど気持ちを抑圧することにより、処理されない感情が心の中に蓄積している状態のことです。
ストレスの経過にはイライラしたり、異様に肩こりなどで体から危険信号(交換神経が緊張状態)が発せられる「警告期」、疲労感が興奮に繋がったり、逆に脱力感に陥る「抵抗期」、疲れきり、長期に渡るストレスに耐えきれなくなり消耗し、本当の病気に移行する「疲弊期」の3段階で進行します。
| 心理的症状(抵抗期) | 身体的症状(警告期) | 主な病気(疲弊期) |
| イライラ、感情的になる、精神的に不安定、漠然とした不安感、気分が落ち込む、憂鬱、注意力や集中力の低下、無気力、新しいことに消極的 | 偏頭痛、腹痛、胃もたれ、便秘、下痢、肩こり、腰痛、動悸、めまい、手が震える、生理不順、倦怠感、疲れやすい、疲れがとれない、寝つきが悪い、目覚めが悪い、夜中に目を覚ます、朝起きることができない、食欲不振 | 胃潰瘍、胃がん、十二指腸潰瘍、過敏性腸症候群(腹痛、吐き気、慢性的な下痢、けいれん性便秘など)、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など) 自律神経失調症(めまい、動悸、のぼせ、肩こりなど)、心身症、神経症、うつ病、がんのリスク |
一方で良いストレスというのは、何かを達成させる原動力になったり、何かを頑張るための適度な刺激になります。目の前の課題や試練(ストレス)をクリアすることで人間的に成長できたり、充実感や達成感、満足感を得られるのは良いストレスになります。
ストレスが脳に与える影響
私たちはストレスを受けると、思考や行動をコントロールしている脳の大脳皮質前頭前野に影響し、その隣にあり本能や感情と関係の深いと呼ばれ大脳辺縁系がそのストレスに対して不快と感じ、間脳を通じて自律神経を緊張させます。
そして、脳全体に突起を伸ばしている神経からドーパミンなどの神経伝達物質が放出されます。これらの濃度が前頭前野で高まると、神経細胞間ネットワークの活動が弱まり行動を調節する能力も低下します。
さらに視床下部から下垂体に指令が届き、副腎がストレスホルモンであるコルチゾールを血液中に放出され、同時にアドレナリンなどが分泌されます。このコルチゾールとアドレナリンは、血糖値や血圧の上昇、免疫抑制、胃酸の分泌促進などを引き起こす作用があります。この働きによって交感神経が優位になり、副交感神経とのバランスが崩れていきます。
ストレスとの付き合い方
心の疲れというのは、体の疲れや病気とは違い目で見て分かりづらいものです。骨折すれば歩けないから一時的に休む必要がありますが、心の疲れは気づかずに見逃されてしまうケースが多くあります。そのため、以下のような休んだ方が良い限界サインを見逃さないでください。
- 眠れない、朝早く目覚める
- ドカ食いするまたは食欲がない
- やる気がでない
このような限界サインが現れたら、正しく休むために嫌な感情にラベリングして心の中に目をむけるという「感情ラベリング」という方法があります。心の疲れを取るためのファーストステップが、自分の中にどんな感情が出てきているかを正しく知ることです。そのために自分の心の中を客観的に見つめることが必要です。
自分の感情を言葉にできないと自分の気持ちを整理できず心の疲れが取りづらくなってしまいます。例えば自分はイライラしていると言葉にできないと、なぜ自分はイライラしているのかという原因に目を向けることができず、当然イライラを取り除くことも難しくなります。自分の中にどんな感情が生まれているのかを気づくために、自分の心の中を観察することが重要になります。
そのために自分の感情に名前をつけるのが「感情ラベリング」です。例えば気持ちがもやっとしているのであれば「モヤモヤ」、何かにムカついているのなら「ムカムカ」という風に言語化して下さい。これによって自分の感情に変化が起きた時に気づきやすくなります。
その次にできるストレス解消法が「ネガティブ・ダストビン」です。自分のネガティブな考えを書いて、それを破ってゴミ箱に捨てるだけです。実際に研究では、これだけでネガティブ思考からくるストレスが和らいだという結果が出ています。なぜなら人は考えや感情を紙に書き出すとそれが実体のあるものになったかのように思い込むからです。そして考えを書いた紙を破り捨てることで実際にその考えがゴミとして捨てられたかのように脳が捉えてくれます。また頭の中にあった感情を全て吐き出すことができるため、頭の中の悩み事を外に吐き出すことでストレスを発散することができます。
最後に、人間関係の悩みも心を疲れさせる大きな悩みのため、話せば分かり合えるという幻想を消すことが大事です。世の中には、普通の感覚ではちょっと理解しがたいようなものの考え方や捉え方をする人がいます。優しい人ほど分かり合おうとしますが、いくら話し合っても分かり合えないことが多いです。世の中には分かり合えない人もいるから仕方がないと割り切ることが大事です。
また、愚痴や悪口を言う人と極力関わらないようにし、自分自身も愚痴や悪口を言わないようにすることが大切です。愚痴を聞くと疲れてしまうのは、脳の中にミラーニューロンという神経細胞があるからです。ミラーニューロンには、一緒にいると相手の感情を読み取って自分も相手と似た感情になるという性質があります。そのため愚痴が多い人と一緒にいると、ミラーニューロンが相手のネガティブな感情を読み取ってしまい、自分にもネガティブな感情が出てくるため不快な思いをしやすくなります。実際に研究でも、人は怒っていたり不安な気持ちになっていることを言葉や態度で表している人を見ると自分もその人と同じ気持ちになりやすいことが分かっています。
意志力に頼らない
一般的に、自分自身を律して自己コントロール能力を発揮することが重要であると言われています。もちろん努力をすることが大事であるのは間違いありませんが、努力や自己コントロール力に頼るのは危険であることは研究が示しています。例えば意志力を振り絞って努力をすると 寿命が縮んだり、老化してしまうことが研究によって示されています。
その理由として、意志力を振り絞って懸命に努力することによって多大なストレスが掛かるからです。過度なストレス環境では、副腎からコルチゾールというストレスホルモンが分泌されます。このコルチゾールは短期的には集中力を高める良い作用がありますが、長期的には老化を加速させてしまいます。さらに長い間ストレスに晒されることによって体内でフリー ラジカルと呼ばれる 活性酸素が増加します。このフリーラジカルは細胞の構造や機能に悪影響を与え、病気のリスクを高めたり、老化を促進するとされています。
また、長期的なストレスは細胞のDNAにダメージを与えるということも分かっています。これによって細胞の修復能力が低下し、老化が加速します。さらに意志力を振り絞って懸命に努力をすることによって心身の疲労が蓄積し、睡眠の質が低下します。睡眠は体の修復や回復に重要な役割を果たしており、睡眠の質の悪化や睡眠不足は老化を大きく加速させてしまいます。
一方で、長期的なストレスは免疫機能にも悪影響を及ぼすということが分かっています。免疫機能が低下してしまうと感染症にかかりやすくなり、細胞の老化が進んでしまいます。
意志力を振り絞れば不可能も可能になる。努力さえすれば何でも叶うという夢物語を信じすぎている傾向にあります。現実的にはそんなことはなく、私たちの多くは遺伝的な要因、環境的な要因によって規定されているということが明らかになっています。どんなに頑張っても、すべての混乱を乗り越えるのは不可能ですし、例え困難を乗り越えて成功したとしてもストレスによって病気になったり、老化が速まってしまうということです。
この残酷な真実の前にできる、おそらく最も良い解決策は意志力を振り絞らなくても出来ること、意志力を振り絞らなくても継続できることを見つけるということでしょう。自分のことをよく分析し、自分はどんなことならば苦労なく続けることができるのか、どんなことならばストレスなく頑張れるのかということをよく考えることが大事です。
粘り強く努力を続けられる力が、スポーツ選手やビジネスの世界、学業などあらゆる分野で成功するための鍵であると言われています。しかし自分の向いていないもの自分の嫌いなものに対して、粘り強く努力することを発揮してしまうと、あらゆる健康上のリスクになってしまうことに注意しましょう。
長期的なストレスを放っておく
長期的なストレスは細胞の寿命を図るマーカーであるテロメアの短縮を促進するということが示されています。テロメアは染色体の端にあるDNA領域のことで細胞分裂の度に短くなります。テロメアが短くなると細胞は老化し、機能不全になり、最終的には死に至ります。そしてストレスによる酸化ストレスと炎症がテロメアを修復する酵素の活性を低下させ、テロメアの短縮を促進するということが分かっています。このようにストレスはDNAレベルで老化させてしまいます。
長期的な慢性的なストレスによって、体内ではコルチゾールやアドレナリンなどのストレスホルモンが分泌され続けます。こういったホルモンは、短期的にはエネルギーを出し集中力を高めてくれますが、長期間分泌されていると酸化ストレスや炎症を引き起こし、細胞の損傷や老化を引き起こしてしまいます。またストレスホルモンを分泌する副腎がずっと働き続けることになり、副腎疲労に陥ってしまう可能性もあります。また長期的なストレスは自律神経を大きく乱し、交感神経が活発に働き続け、血圧が上昇して心血管疾患のリスクが増加します。さらに炎症反応が高まり、老化や慢性疾患の発症につながります。
毎日が退屈で老化
退屈というのは非常に健康に悪いことが研究によって示されています。例えば 退屈はストレス反応を引き起こすということが指摘されています。このストレスによって病気のリスクが高まったり、老化が促進されてしまいますが、退屈だと私たちはついつい不健康な行動をとってしまう可能性が高まります。また退屈で刺激のない状態だと脳が老化してしまいます。
退屈な状態は脳が新しい情報や新しい刺激を受ける機会が減少しているということに他なりません。研究では脳の刺激が認知機能を維持し神経細胞の新陳代謝を促進するということが示されています。従って長期的な退屈が脳の刺激不足を引き起こすことで脳の老化が進行する可能性が指摘されています。さらに退屈が死亡率を上げてしまうという研究があります。
例えば2010年に行われた研究が注目されており、この研究の結論だけ述べると退屈が心血管疾患や他の健康問題を引き起こし死亡率が上昇してしまうということが示唆されました。退屈を感じることが死亡率に影響を与える可能性のある理由として、退屈がストレスや不安、抑うつなどのネガティブな心理的症状を引き起こすということが挙げられています。こういった症状は心血管疾患のリスクを高めるということが一般的に知られています。また退屈を感じている人々は興奮や刺激を求めて喫煙、過度の飲酒、暴飲暴食、薬物の摂取などの健康に悪影響を与える行動をとる可能性があります。こういった行動が死亡率を上昇させる要因となると考えられています。
ストレスと睡眠
健康的とされている睡眠時間は1日7時間から8時間と言われています。睡眠の質が悪くなると私たちの体は、ストレスやうつなどの精神的な悩みにつながります。特に眠りたいのに眠れない場合は、イライラしてストレスが溜まり、そのストレスでまた眠れなくなるという悪循環に陥ります。
リラックス効果のあるアロマオイル
眠りを妨げるイライラを抑えるためには、リラックス効果があるアロマオイルを利用することをお勧めします。ハーブから抽出されるエッセンシャルオイルを使用したアロマセラピーは、脳と体へのリラックス作用やストレス軽減作用があると言われています。
例えば、お風呂に入る時にお湯にアロマオイルを数滴垂らしたり、寝室でアロマを焚いたり、水とアロマオイルを混ぜて枕やシーツにスプレーするといった手軽な方法でリラックス効果を実感できます。
睡眠導入の効果やリラックス効果があるとされている代表的なアロマはラベンダー、ジャスミン、ゼラニウム、シダーウッド、イランイランなどがあります。特にラベンダーは様々な研究で心を落ち着かせて眠りを誘う効果があることが 証明されています。研究によると、ラベンダーオイルの香りを嗅ぐことで血圧と心拍数が低下することが分かっています。またサウサンプトン大学(イングランド)の研究では、ラベンダーオイルの香りがする部屋にいた人は、睡眠の質が平均で20%も高くなるという結果が出ています。
寝る前のハーブティー
ハーブティーには、睡眠導入効果やリラックス効果が期待できます。代表的なのはカモミールティーです。カモミールティーには気分を沈める作用があることが知られています。
例えば、イランで行われた研究では睡眠障害のある高齢者施設の人たちに1日2回カモミールエキス200mg、もしくはカモミールエキスが入っていない物を投与したところ、カモミールエキスを服用した人は睡眠改善効果が見られました。また台湾で行われた研究では、睡眠障害がある産後の女性がカモミールティーを2週間飲んだところよく眠れるようになりうつ状態も回復したという結果が出ています。
これらの効果は、カモミールの花に含まれているポリフェノールの一種であるアピゲニンが脳内のベンゾジアゼピン受容体に働きかけるため鎮静効果があると考えられています。つまり脳の活動が抑制されて眠気や鎮静効果が現れます。
頭の鍼でストレス解消
これらのように、感情(七情)の乱れが身体のどの部位にどう作用するかを診るのが東洋医学の特徴です。東洋医学では、過度な感情の動きが気の動きに変化をもたらし、関連する五臓や身体に影響を与えることが見いだされていました。
いずれにせよ心と身体を分けて考えるのではなく、むしろ身体の一部が心である、あるいは身体の一つの部分が心であると考えることができます。心と身体は分けることができない、身体が疲れれば、心も疲れますし、身体が休まれば、心も休まります。
身体を大事にすることで心が健康になる。身体に無理をさせることは心に無理をさせることになります。心を健やかに保つことが万病さえ起こさせない可能性があることが分かってきています。
そして臓腑(五臓六腑)に繋がる経脈上のツボを刺激し、経絡上の気の流れを調え、臓腑(五臓六腑)を整えることは、結果として精神面の調整にも繋がるのです。また生理機能として、人は、ストレスを感じると脳の血流が低下します。このストレスがストレス疲れになり「疲労感」を生み出します。
近年の研究では、鍼が身体の正しい箇所に施されるとストレスホルモンの伝達を抑えることが分かっています。つまりストレスに対処する薬の多くと同じく、鍼もストレスホルモンに対して薬と同じように作用します。特にストレスによる諸症状(不眠症、自律神経失調など)に対して頭の鍼はよい効果が認められています。
頭の鍼治療を受けた多くは、様々な症状の軽減とともに、独自の爽快感を体感し、ストレスの緩和に最も適した治療法の一つになります。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。